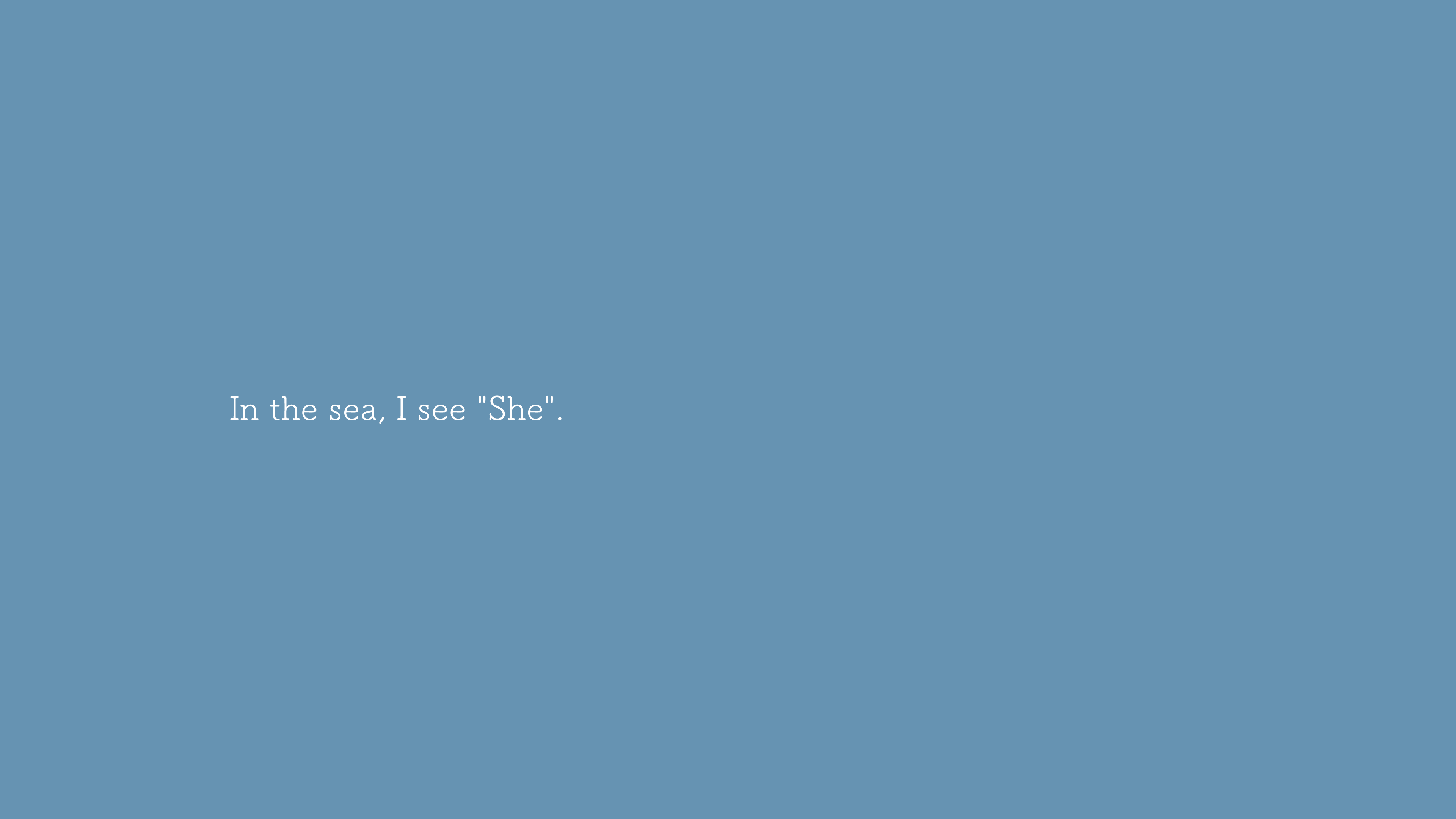視界の端に人がいる。
「あ」と、どこからか澄んだ声が聞こえたような気がした。
いやいやいや待て待て。この季節に同じ場所に人がいるだなんて本当の本気で予想だにしていなくて、私は思わず立ち上がって「何してんだ!」と彼女の腕を掴んだ。
二月の海、入水自殺失敗の瞬間である。
その時の彼女はあんまり驚いているようには見えなかったけど、にんげん本当に感じ入っている時なんて表情へのフィードバックが薄くなるもんだ。だから、流石に驚いてなかったわけじゃないと思う。
海水の冷たさで指先を震わせながらおとぼけ顔をかましている脳天気な女には正直本気でグーパンをかましてやりたいところだったけど、冷たい海に沈んでいた私の体は彼女以上に深刻だった。錯乱する頭で何を答えたのかは正直覚えていない。
私が波打ち際からきちんと歩いて陸に上がれたとは思えないから、きっと彼女が引き摺り上げてくれたんだろう。
五つの音、変な音、低いのが二回、元の高さに近いけど何言ってんのかわかんない音が一回。ダイヤル音だ、きもちわるい。
「なに?」と、尋ねるのに数秒を要した。思ったよりも大きな声が出た。止めようとして、震えて、そう発音できているのかも曖昧だった。体が思うように、動かない。
彼女の手元にはスマートフォンの光が見えた。
#7119
「……あ、はい。海で人を見つけました。今は陸にいます」
「いつから海に入っていたのかは分かりません」
「はい、意識はあります。話せてます」
「歩いてましたけど、震えが強いです。真っ直ぐ進めないと思います」
「顔色が真っ青です。唇も紫になっています」
「呼吸は早いです。震えてて、浅いというか、」
「タクシーなら呼べます」
「はい、付き添えます。わたしは高嶋と言います」
そこでやっと、私の番が回ってきた。振り返った彼女が私の目を見た。
「あなたのお名前は、」
「あー……あぁ、みやもとかなで、です」
名前、と聞かれて、いくつかある名前の中の、一番くだらないものを挙げた。
スピーカーホンに変えられた電話口の声があんまり聞こえてる気がしなくて自信がなかった。ジージーとザーザー、高い音がどこかで鳴ってる。電話が怖かった。無機質な機械の音がする。
『ミヤモトさん、生——日、——ますか、』
電話越しに、聞き取れない音がたくさん響いている。何を答えればいいのかがわからない。
けれど困り顔の彼女には体温があって、電子を介した音が聞こえなくっても目の前にいる彼女に話せばなんとかなるのかもしれないと思うと、強張った体から少しだけ力が抜けた気がした。
会話が正しく成立しているのかもわからない私の電話の応答をしばらく見つめて、彼女はまた電話に意識を戻す。私の年齢や性別を電話口に伝えて、それから「はい、やってみます」という大変不思議な言葉で通話は切られた。
冬の海に入る非常識な彼女はご親切にも真っ当な人間性を持ち合わせていたから、自殺未遂者の救急相談という世間様には大変申し訳ない事案の片棒を担いでくれた。
彼女は手近なタクシー配車アプリを使って面している道路にタクシーを呼んで、それを待っている間に私の服を脱がせた。
「脱いで」
「あええ!?」
冷たい潮風に吹かれると余計に体温が奪われるから仕方のない対応だったらしいんだけど、説明を受けたはずの彼女は事前に何一つ説明しなかった。意識が混濁している人間にそんな言葉は必要なかったのかもしれないけど。流石にびっくりした。
私の尊厳が破壊され尽くしたあと、彼女はコートを貸してくれた。彼女は華奢だし二月の寒空の下でアウターを脱いで寒そうだったけど、絞れるほどに濡れている自分の服を着直すのは物理的にできなかった。手足が震えすぎていて、物を持つことさえ叶わなかったからだ。
それから、彼女は夏には利用者も多いであろう自販機からホットのペットボトル紅茶を買ってくれた。
間も無く着いたタクシーでは暖房が強めにかけられていて、私たちの様子を見て慌てた運転手からはたくさんの毛布を受け取った。配車の時点で彼女と運転手が気を回してくれていたらしい。少しずつ、少しずつ私は温まって、だんだん心臓の負荷を感じるようになっていた。
チリチリと痛みだした指先と、バクバクと鳴って痛む心臓が苦しくて体を縮こまらせていたら、彼女はコートの下に腕を忍ばせてくれた。同じ空の下にいた冷たい彼女は、それよりもずっと冷たくなった私に体温を貸してくれた。
「今日は楽器持ってなくてよかったな」
と、聞いたのが本物か幻聴か私にはわからなかった。だって、低体温症ってそういうものらしいから。
道沿いに見つけた海岸で、私はあのときのことを思い出す。
冬の昏い灰色の海。
あまりに綺麗だから指を弾ませながらインスタに写真を載せたら、友達からの「いいね」に紛れてLINEに通知が入っていた。そっけない風を装って心配している母からだ。
『海には入らないでよ?』
娘のインスタ見てるのか、キモすぎる。仕方がないので、私は短く返信を打った。
耳をすませば押しては返す、砂と水の擦れあう音が繰り返される。ひたすらに続く、噪音 。それは強くなったり弱くなったりしていて、波がある。波の音に対して「波がある」なんておかしな言葉だけれど、変化し続けることを表すのに、波以外の言葉を私は思いつかない。
潮騒に耳を澄ませていたら、一瞬だけ周囲の音が止まった。
はっと驚き振り返った視線の先に立っていた彼女は、大きくて黒い魔物に襲われているみたいな人だった。遅れて理解する。……あ、ギターケースか。でっけ。
「あれって自殺だった?」
「とんでもないこと聞くじゃん」
下がった眉が流行りの絵文字みたいな可愛い顔でとんでもねえ第一声を発したから、思わず私もタメ口で返してしまった。
年上の、綺麗な女の人だ。
初めて明瞭な意識の状態で出会った命の恩人は、見た目と雰囲気からもう絶対にあの時死ぬ気はなかったんだなと理解した。思わず世話焼いて死に損なったのは自分だけだ。
彼女が死のうとしていなくて、よかったと、心底思った。
「っていうか、すごい。私のこと、私だってわかったんだ」
「聞こえてたからね」
「何が?」
「うたが」
「……そう、さぞかしノイジーだったでしょう」
「そうでもないよ」
あとから私は「名前、なんだったっけ」と付け足す。
多分電話口で名乗ってたけど、一度聞いたくらいじゃ覚えられない。私はただこの人があの時助けてくれた人だと『わかった』だけで、彼女のことを覚えてるわけじゃない。
彼女も眉を下げて「わたしも聞いていい?」と笑う。ああよかった自分だけじゃないんだ、と、それにひどく安心して、改めてお互いに自己紹介をした。
道を遮っているわけにもいかないので、私と永句ちゃんは結局浜辺に移動した。
「海岸近くで見る? 死にたくないなら、止めるけど」と聞かれた時には驚いた。彼女なりに自殺志願者のストッパーになってくれているのは確かで、けど永句ちゃんはとっくに浜辺へ降りる階段に足をかけていた。
先を歩く永句ちゃんを背に、私は階段を降りてすぐの自販機でペットボトル紅茶を買っていた。寒さに震えていない時に飲むペットボトル紅茶は信じられないくらい甘ったるい。真上から照りつける太陽は遠く、風に運ばれてくる冷気のほうが確実で、耳をくすぐるような波の音が彼女を包んでいて、私の舌には甘い船が乗っている。波を、感じている。
「海、好きなの?」
私は最初に、一番気になっていたことを永句ちゃんに聞いた。
「好き。……それ、どうして聞いたの?」
「永句ちゃんが自殺志願者じゃなかったから、かな」
ふふ、と永句ちゃんは笑って(これはたぶん「あなたがそれを言うの?」と問う仕草だ)、それから手頃な浜辺の柵に腰をかけた。海岸からは、まだ少し遠い。
「あ、ギター弾いてるところ見たい」
感想は言えないかもだけど。その一言を私は飲み込んだ。
永句ちゃんは背にかけていた黒い魔物……もとい、楽器ケースからギターを取り出して、ストラップを肩にかけた。流れるように自然な動作に、慣れているんだな、と思う。
「あの時海にいたのは海が好きだからだけど、入ったのは奏がいたからかもね」
私がいたから? てか名前呼び捨てなんだ。確かに多分、私の方が年下だけど。
弾かれた弦が空気を揺らす。普段は耳障りなほどよく聞こえる波の音が遠くに聞こえていた。海はすぐ近くにあるのに、遠くに聞こえる。変な感じだ。
彼女の手は悴んでいるだろうに、ゆっくりと動く指先は一定のリズムを刻んでいた。
「変わったうただったから、気になって追いかけたの」
「だからって冬の海に入るかね?」
「そんなつもりは無かったんだけど」
「それでも、冬の海には入っちゃダメだよ。音楽をするなら、なおさら」
こればかりはほんとに、私が言えた話ではないのだが。
永句ちゃんの周りにはきっとたくさんの音が溢れているのだろう。この海のように。
海での逢瀬は思いのほか早く終わった。
「寒すぎる。ギターを弾いてもらうにも寒すぎる」
「手が悴んじゃって」
二月の海、潮風って思ったよりきつい。私ってこんなのに見舞われて生き延びたのか。生き汚すぎる。
とにかく私たちは都心に戻ることになった。最初は近くのカフェでも入ろうかって思ったんだけど、海沿いに案外入りやすいカフェはない。都心でギター弾けるところってどこなんだろう、と考えながら慣れない改札を通る。普段は使わない路線だ。
乗った電車では窓の外を見て、永句ちゃんは一旦海の見える方に座った。
「永句ちゃんはMRIって撮ったことある?」
「時間かかるよね」
「なんか、後遺症の検査で頭を撮ったんだけどね。すっごいガチガチに固定された」
「わかるよ、私も頭だった」
頭だったんだ。
絶え間なく響く車輪の音、時折挟まるブレーキとカーブで軋む金属。
私は永句ちゃんの声に耳を傾け続けた。もとよりそれなりに居た人がどんどん増えてきて、おしゃべりしているのも少し悪いかな、と思いながら私はぽつぽつと話を続けた。
「ギターってどこで弾くものなの?」
「どこでも弾くかな、公園とか」
「ギターってすごい」
抱えるケースはでっかくて重そうだけど、案外小回りが効くらしい。確かに、砂浜でも弾けるんだったら東京のどこでも弾けるのと変わらないだろう。……てか、そうじゃない。そういう話をしていたんじゃなくて。
「寒いから公園とかじゃ弾けないかなって話だよ」
「地元の児童館でもいいし」
「え、地元どこ」と思わずノータイムで返した私に「吉祥寺の方」と同じくノータイムで返答する。
ぐうぅ。
永句ちゃんに返事をしたのは私の腹の虫だった。「そりゃいいね、行こう」と気のいい返事を返したかったのに、午後二時半。顔が熱くなるのがわかる。もう東京に居る。だから当然、周りには人がいた。どきまぎしながら震える唇でどうにか声を出した。
「……カフェに寄ってからにしない?」
永句ちゃんは口元に手を当てて(絶対笑ってる)、それから「うん。賛成」と穏やかに言った。
ふだんで言えばどう考えても乗り換えにしか使わない駅で永句ちゃんは改札を降りて、ほどなく歩いた先にあったのは青い扉の小さなカフェだった。
看板だと思わなければただの表札にも見える扉を開いて(Subsea、縁起の悪い店名だ)、カランカランと金属音を立てたドアベルの音がそこをようやく店だと印象付ける。
「人がいなければ、ここでも弾けるかなって」
遅れて奥から出てきた背の高い男性が「妹さんだ。こんにちは」と馴染みらしい挨拶をしていた。確かに、平日の真昼間といえどレジのトレーを開けたままカウンターを放置するような店主がやっているカフェで楽器を取り締まる法律はないだろう。……そういう問題ではないか。
「げ」
と、声に出さなかっただけ、その時の私は偉い。
商売っけのない店主を差し引いても楽器が弾ける店というのは頷ける。店の奥にはモーター音を響かせて回転しているレコードと茶トラの猫。それから。それから、隅に置かれた茶色い小さなアップライトピアノは、私の顔馴染みだった。
顔馴染みだった。相棒と言ってもいい。相棒と思ったことは一度もないけど、親からそう言われたことはある。
私は大急ぎで視線を逸らして近くのソファ席に座る。
頬が引き攣っていないか、気になる。そうでなくても楽器をやっている人の中には他人の機微に聡い人がいる(そうでなければスカポンタンの朴念仁が多い)。永句ちゃんが聡いほうか疎いほうかなんて気にしたって仕方がないので、私はナポリタンとカフェオレを注文した。
レコードが回っていた。それが何を再生してるかは、わからない。
電車移動が楽しかった余韻が衝撃に吹っ飛ばされた私をよそに、永句ちゃんはランチメニューに悩んでいる。海にいた時間的に永句ちゃんも昼抜きだからそりゃ頼むだろうけど、テキトーに大急ぎで注文決めてごめん。……あ、カルボナーラなんだ。
「永句ちゃんって妹なの?」
「うん、兄がひとり。双子だよ」
「へえ、そりゃ立派なお兄さんなんだろうね」
「そうだよ」
あ、笑ってくれた。
「てか私ばっかり質問してる? ほぼ初対面で超怪しい人? いやそれは一緒に電車乗った時点で自明の理じゃんね絶対関わらない方がいい人だよね、私ね元自殺志願者だしね」
「元なんだ」
永句ちゃんはてっぺんに乗った黄身を潰しながらさらりと言った。
「そう。……元、だよ」
元、と改めて言った私に対して誰もが言う取ってつけたような「良かったね」という言葉は返ってこず、代わりに永句ちゃんが口元だけで「もと」と小さくつぶやいたのが見えた。私が『元』自殺志願者であることを永句ちゃんが二度も確認したのは、ほんの少し意外に思えた。
「じゃあ、聞いてもいいかな?」
「うん?」
「どうして死のうと思ったのか」
「永句ちゃんって面白い人だね」
私は珍しく、嫌味なくそう思った。楽しいと言い換えてもいい。面白いと思わない相手が聞いていたならそれは多分大変なことだったけど(たとえば私の母親とかね)、私は楽しいと思う方だから問題がない。
永句ちゃんの手元でくるくるとフォークに巻き付けられたパスタがソースを皿に滴らせる。パスタの食べ方がわかっている人間は好きだ。
「教えたげる」
「うん」
「その前に、ギターを聞かせてくれたらね」
語るには、私の手元に必要なものがなかった。だからそれはご飯の後。
指先も温まったことだろうし、他に客はいなかった。顔馴染みのようだし、店も快くこの場所を貸してくれるだろう。
(頼んだはいいけどナポリタンとは何ぞや?)と裏でこっそり画像検索していた私の想像を、運ばれてきたこの店のナポリタンは二段階ほど裏切った。多分これはグーグル先生が教えてくれたケチャップの安っぽい味ではないやつで、細かく切られたトマトの果肉が見える。そういえば「ナポリタン(ポモドーロ)」みたいに書いてたっけ、メニュー。ポモドーロを検索すると、手元にある実物と近い画像が表示される。どっちなんだよ。
「……あ、美味しい」
時には焦って興味ない選択肢も取るもんだな、という教訓を得た。
けど永句ちゃんの食べるカルボナーラも美味しそう。ソースが滴ってるし。期待感だけが煽られている。潰れた黄身の流れる様から視線を逸らせずにいると、永句ちゃんはまた笑ってくれた。
「また来れば食べられるよ」
「そう、だね」
また。
そんなに量の多い食事ではない。ワンプレートのパスタを私たちは早々に食べ終わって、店主は「人が来るまで好きに使っててね」と適当なことを言った。店の中で使ったものは後で確認してレンタル料を払うらしい。多分、借りられる機材にはあのピアノも含まれているのだろう。珍しい茶色の塗装で、店に置かれているにしては傷の少ない、あのピアノが。
永句ちゃんが海の時よりも強めにギターの頭についてるネジを締めて、チューニングは多分完成だった。
「一応……何の曲がいいとか、ある?」
「曲とか、知らないんだけど」
知らないってのは嘘だ。古い曲なら知らなくもない。けど別にそれが聞きたいわけじゃないし、多分通じないし。彼女が言ってるのはヨルシカとかヨネヅとかそういうやつだろう。それは本当に私が聞いたことないやつだ。
そのギターは、波のような仕草で奏でられた。弦に添えられた右手が上に行ったり下に行ったりしている。
「じゃあ、即興で」
「即興!?」
しまった、思わず大声。ハッと口を手で押さえるが、もう遅い。レジのトレーをついぞ押し込まないまま奥に引っ込んだ店主が出てきて、私は小さな声で「大丈夫で〜す」と中途半端に笑った。永句ちゃんも「気にしないで」とよく通る声を飛ばす。喧嘩じゃないです。
その間も左手の指先だけは、楽器から離れることはなかった。金属の弦から爪弾かれる音は変わらず波のようだった。
「カヴァーの方が良かった?」
話を本題に戻すように、店主に向けたのより少しばかり近くに響かせた音が私に向かって飛んでくる。曲を即興で選んでジャジーに奏でてくれる、という線もあったけど、今の会話でその可能性も消えた。
「なんか、想像もしてなかったから、びっくりして」
「まあ、珍しいかもね」
永句ちゃんが分厚いギターの本体をトントンと叩いて、演奏が始まる。
ただ音を鳴らしているわけじゃない。これが「演奏」の始まりだと丁寧にお膳立てされていた。
ネックに触れる指はいくつもの弦を同時に押さえていて、金属の部品の必要性がわかった。一度にこんな和音を響かせるには、確かにこのやかましい銀のブリッジが必要だろう。押さえるたびに小さくカチカチと無駄な音が入るが、それでも必要だった。
今までの会話、ほんのり冷たい彼女は演奏している間、必要もないのに自分の手元を時々見る。小指の先で私を指した。この小指は私を指しているんじゃなくて、弦を爪弾く腕のストロークが宙に浮いたときに向いたものだ。最初はゆったりと和音を響かせていたのが、いつしか親指でギターの本体を叩くリズムの入ったものになる。波のように上下させて和音を奏でていた右腕は、途中からその位置を固定させて指で一つ一つの弦をはじいて音を鳴らしてその様子は金平糖の妖精が踊っているようにも見えた。
演奏の時間はあっという間で、それでいて永遠だった。波が押しては返す。返すときの、あの有り余る力が身体中を襲っていた。
楽しそうだった。だから、それでいいかと思う。
「いいね、それ」
端的に思わず呟いた言葉はあるべき余韻を考慮していない。私なら客席に降りてぶん殴っているところだけど、永句ちゃんはそうではない。夢中になっていた私を見て、見て、それから静かに微笑んだ。
後遺症の検査のために頭を固定されてMRIを撮ってる間、ずっと鳴ってる機械の騒音を何かがずっと和らげてくれたから、死に損なっていてもいいと思えた。
耳は閉じられなかったけど、和らいだのは確かだった。
今も同じだ。電車も海も、音の絶えない空間で、私には耐え難い。そのはずだった。
二杯目のドリンクはアイスにした。
面白いものを見た直後で興奮がおさまっている気がしなかった。アイスといってもアイスコーヒーだ。もちろんラテにした。苦いものを苦いまま飲むのはもっと味蕾が死んでからでいい。
永句ちゃんは小洒落たクリームソーダを頼んでいた。くそう、それ、私も今度頼む。
「私が死のうと思ったのはね、世界中のみんながうるさいからなんだ」
「へえ、そうなんだね」
聞いておきながら永句ちゃんは本当にやる気のない返事をした。永句ちゃんって友達少なそう。ギリ暴言かも。いや私友達少なくないから相対的に多分セーフ。今も死にたい人が聞いたらその場で首吊って死ぬんじゃないかってくらい適当な返事に聞こえたけれど、彼女にとっては大真面目に適切な相槌だと思ってるみたいだった。言ってる場合か、話が進まないんだっての。
そもそも死のうと思った理由なんて、聞かれて答える方が馬鹿げているのだ。
可愛いカップを置いて私は茶色いピアノの蓋に触れる。彼は相棒、と呼ばれたことのあるただの楽器だった。十年ほど前に私の前からいなくなったけど、弾かなくてもわかる簡単なこと。私が癇癪を起こして蹴り飛ばした、その跡がくっきりと残っている。
とんでもない偶然だけど、私が永句ちゃんをあの海で見つけた時が偶然の最高潮だ。だからそれはもうこの際、どうでもいい。
久しぶりに開いたピアノの蓋は案外と軽くて、自分でピアノの蓋を開け閉めしたのなんてそもそも数えるほどだったなと振り返る。普通は黒く塗装されている外側が素材の木目なだけで、開いてみれば普通のピアノだ。白と黒で塗装されていて大変わかりやすい。
四歳の頃にグランドピアノを貰ったから、必要のなくなった私の相棒。埃をかぶって、いつの間にかどこかに行った私の楽器。
「ゲネプロ……リハーサルの最中、ピアノの音が聞こえなくなっちゃって」
「うん」
「ていうか、音楽が、消えたんだ。今も基本、聞こえない。脳の障害なんだってさ」
「そうなんだ」
これは結構最近の話だ。ここ二年くらいの。
音が聞こえなくても、実際のところピアノは弾ける。他の人は知らないけれど、私はそういう風にできていた。
初めてリサイタルをやったのは六歳の頃だった(リサイタルという言葉に馴染みのない人には、単独コンサートと言い換えてもいい。私はその中心にあったというだけで、ピアノを弾く以外は何もしていない)。私に新しいものは何も必要ないし、聞こえている必要は一つもなかった。自分の鳴らす音や新しいものが必要な演奏家は周りにたくさんいたけれど、私はそうじゃない。
永句ちゃんみたいに即興で演奏するなんて考えたことがなかった。楽譜がある。ひたすらに正しく、演奏するだけ。
「音楽好きだったっていうか、好きじゃないんだけど。……好きじゃないのに、」
好きとか嫌いとか以前に、だってそういうものだったから。
「音楽が無いと、何もかもがうるさくってさ」
それが嫌で、ずっと嫌で。耐えられなくなったから冬の海に身を投げたんだよ。
普通じゃない話をいくつもしたけど、やっぱり永句ちゃんは学校で同級生の愚痴を聞いてるみたいに軽い相槌を返した。
——そういえば、永句ちゃんからは「どうして死のうと思ったのか」を聞かれたけれど、どうして死ぬのをやめたのかは聞かれていない。話す必要ないのかな、とほんの一瞬考えて、深海よりも黒々とした瞳と視線が合った。多分絶対、ほぼ確実に永句ちゃんはそんなこと思ってなかっただろうけど、「それで?」と続きを促しているようにも見える視線だった。
「けれど、今日は凪いでいたんだ。永句ちゃんと話した時、ほんのちょっとだけマシになった。
だからもう、それでいいかと思って」
やたらめったら主張する波の音はボリュームを下げて、打楽器より耳を破壊する厄介な電車は多少融通がきく相手になった。主役を際立たせるみたいに、さっと道を譲っていった。会話してると周りの雑音が聞こえづらくなる現象ってあるでしょ。それです、それ。
永句ちゃんは不思議な人だ、と思う。多分。
不思議というには少し神秘が足りないけど、少なくとも狂っていて気楽だった。再会した時に「どうして海に入ってたんですか?」「変わったうたが聞こえたからですね」なんてQ&Aを返したのだ。変すぎる。
「うた、がどうとか言ってたけど、うたはずっと聞こえるの?」
「うん」
「私のうたも聞こえる?」
「うん。たくさんね」
「弾くの?」
「え?」
「奏のピアノ、聞きたいなと思って。わたしには弾きたそうに聞こえたから」
「そうかなぁ……。そうだと、いいな」
背後からゆったりとした波のような和音が、その波のまま私の耳に届いた。え、うそ。と永句ちゃんの方を思わず見て、ずっと薄らな笑みを浮かべている彼女はソファの隣に置いていたアコースティックギターを腕に抱えている。あれ、クリームソーダはどうしたの、飲み切った?
「楽譜、今から作ろうか」
こともなげに言ったその笑顔がなんだかおかしくて、私はまた笑った。
試しに指を滑らせた。打鍵感は重い。あ、440 Hz。
そうか、彼も変わっているのだ、と気がついた。手元のピアノはもう私が知る彼の音ではない。この町で演奏されている。それは少し意外な事実だった。店に置かれるピアノは乱暴に扱われるものだとばかり思っていたから。
「この店、よく来るの?」
「時々かな」
「お客さん、入ってる?」
「入ってる、と思う。時々イベントやってるよ」
じゃあ、私も時々弾きに来ようかな。